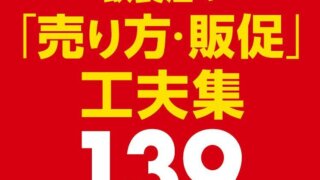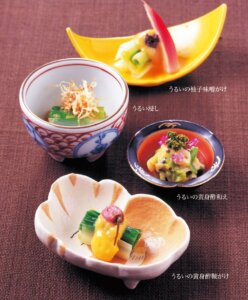中国の餃子が日本で発展した理由とは
日本における餃子の普及は第二次世界大戦後。大戦中、満州に渡った人たちが現地で食べた餃子の美味しさが忘れられず、大戦後も日本で作って食べるようになったといいます。
しかし中国で「餃子」と言えば、水餃子か蒸し餃子のこと。伝統的に北京などの北方地方で茹でた「水餃子」が広東などの南方地方では蒸して火を通す「蒸し餃子」が好まれます。
中国の餃子

中国では、あんは野菜より肉が多いです。特に北方では肉手一番使われるのは羊肉。羊肉には体を温める働きがあるといわれ、寒さの厳しい北方では好まれました。
焼き餃子については食べて残った餃子を使います。中華鍋に張り付けるようにして丸く並べて焼きたことから「鍋貼」と呼ばれました。こうしたことから中国では焼き餃子といえば「残り物」であったため、あまりいいイメージがなかったといわれています。
日本人が満州で食べた餃子とは

日本人が満州で最初に食べたのも、水餃子が多かったでしょう。現地では、長く生活した人たちは中国人の家庭に招かれて食べたり、雇っていた料理人やお手伝いさんが作った料理として食べたりしていました。また兵士の中には、町の市場や飲食店で口にした人も多かったようです。日本人も現地で中国の人に作り方を教わって餃子を作り満州で端役も焼き餃子を作ったり”日本人向け”の味に変えて食べたりする人も。満州では各家庭に日本のお米と同じく当たり前のようにあるといわれた餃子。満州在住当時から餃子の美味しさに魅せられた日本人は多かったそうです。戦後、日本に帰国してもその味が忘れられず、日本で日本人向けの餃子を求め、自ら作るようになりました。
■参考資料:「餃子の探求」(旭屋出版)